新卒採用に苦戦する理由とは
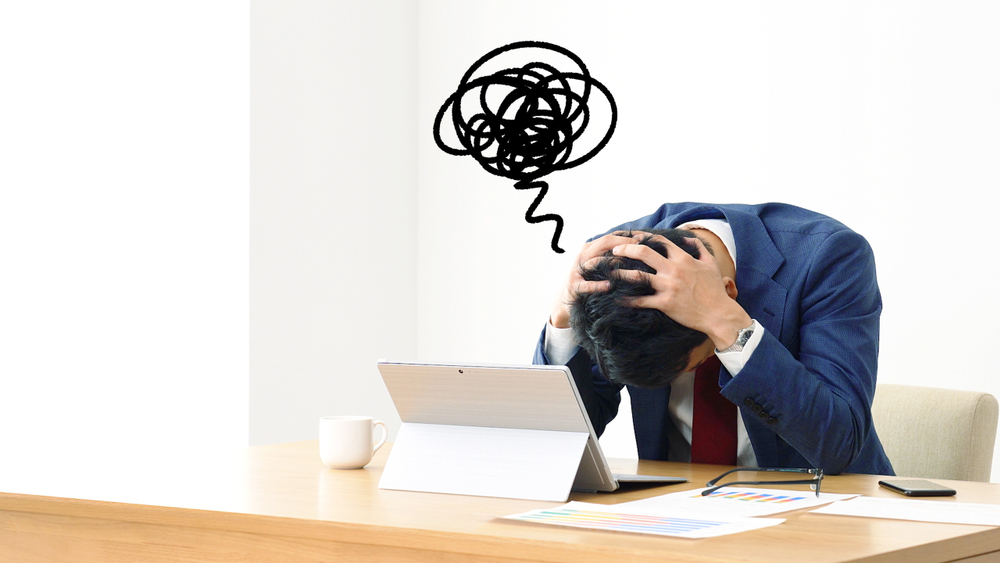
求める学生像が曖昧
新卒採用に苦戦する理由として、まず挙げられるのが、自社に合った求職者が見極められないことによって、求める学生像が曖昧になってしまうというパターンです。 求人内容に記載する人物像、学生像が曖昧だと、求職者側に不信感を持たれ、応募者数も減ってしまうということが起きてしまいます。 応募者数が減ってしまえば、その分、優秀な学生に巡り合える確率が減ってしまい、結果として新卒採用がうまくいかないことにつながってしまいます。
求人内容が適切ではない
次に挙げられるパターンは、求人内容が適切ではないということです。例えば、求人広告に掲載する情報が少なかったり、間違った情報を掲載してしまうといったことです。 求人広告に写真がない、業務の内容が曖昧といった求人内容が適切でない状態だと、求職側である学生に興味を持ってもらいにくくなってしまったり、時には不信感を抱かれることにもなってしまいます。 求人内容は、学生がこれから勤務したいと思えるかどうかを考える上で、重要な判断材料です。しっかりとした情報を掲載することで、少しでも学生の興味をひけるような内容にしておきましょう。
内定までのスピードが遅い
内定までのスピードが遅いということも、新卒採用に苦戦する理由として挙げられます。内定までのスピードが遅いと、休職者である学生に不信感を抱かれるなどして、他企業との採用競争に負けてしまう可能性が出てきてしまいます。 ここでいう選考スピードというのは、選考ごとの連絡が遅いだけでなく、最終面接から内定通知までが長いということも意味します。どちらにせよ、選考スピードが遅いと企業に対する興味関心が薄れてしまいます。 結果として、じっくりと時間をかけて内定の判断を下したのに、いざ学生にそのことを伝えると、採用辞退されてしまうといったことを招いてしまう可能性があります。
内定後のフォローをできていない
新卒採用に苦戦する理由は、内定を出すまでのステップだけでなく、内定後の要因も存在します。中には、内定を得た後、焦燥感や不安を感じてしまい、実際に就職するかどうかを迷う学生がいます。そのため、内定後のフォローは重要な課題となってきます。 ほとんどの学生が、複数の企業に対して求職活動を行なっているので、内定後のフォローがないと学生に、内定を辞退され、結果として他社へ行ってしまわれるということが起きてしまいます。 
新卒採用成功のための戦略

求める学生像を明確にする
まずは、求める学生像を明確にしましょう。求める学生像が曖昧だと、学生に興味を持たれなかったり、不信感を抱かれることにつながってしまいます。 「明るい」「前向き」「やる気がある」といった抽象的な項目で学生を募集するのではなく、求める能力を具体的に明示するということです。 そのためにも、自社がどのような学生を必要としているのか、一緒に働きたい人材はどのような人物なのかということを、社内で徹底的に掘り下げることが必要になってきます。
募集要項を見直す
自社が発表している募集要項の見直しも、新卒採用成功のために必要な戦略となってきます。学生が、得られる企業の情報には限りがあります。そのため、募集要項といった学生の目に留まる部分に配慮することは重要なポイントです。 募集要項は、単にどのような条件で、どのような人材を求めているかといった情報としてだけでなく、文面から企業の雰囲気を感じ取れる部分でもあります。 学生の求職活動にとって、重要な判断材料である募集要項には、業務内容をきちんと記載し、写真などを使用することで、自社のイメージを的確に伝えられるようにしましょう。入社したいと思える募集要項を作成することは、重要な戦略となってきます。
選考のプロセスを最適化する
選考スピードが遅くなってしまうと、学生の入社意欲を削いでしまったり、不信感を抱かれたりしてしまいます。 採用のプロセスが多重化し、選考スピードが遅くなってしまっていると感じたら、自社が行う採用プロセスを見直し、できるだけ無駄を省いた選考を心がけましょう。 選考のスピード、内定を出すタイミングを早めることは、企業にとっては採用コストの低減につながり、欲しい人材が他の企業に行ってしまうことを防ぐのにも有効な戦略です。
内定後のフォローをきちんとする
内定を出したあと、学生を放っておくのではなく、採用担当者などが、積極的にコミュニケーションをとるようにすることで、不安要因を排除してあげましょう。 そうすることは、内定を出したものの、実際に入社してもらえないといったリスクを軽減することに繋がってきます。 
今後取り入れるべき採用方法





